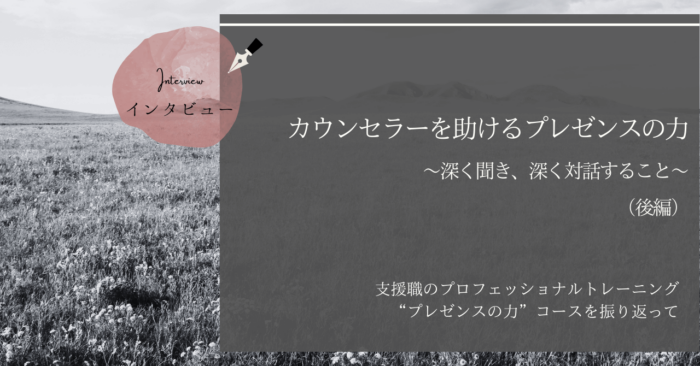International Mindfulness Center JAPANでは、マインドフルネスストレス低減法(MBSR)、マインドフルネスマインドフルネス認知療法(MBCT)を始めとした各種プログラムをご提供しています。その中で、心理支援職に向けたプログラムとして2023年に「プレゼンスの力」を開講しました。
前後編2回の後編です。(前編はこちらより)
このプログラムに参加いただいた、臨床心理士の羽根さんにインタビューをさせていただきました。
(インタビューアー:IMCJ宮本)
前回からの続き・・・
宮本
保護者や先生といった大人の方に対するカウンセリングのあり方はどうですか。
羽根さん
大人の場合も同じで、これまでは聴きながら考えがいろいろ浮かんで「次どうお話しようか」と準備をするような聞き方をしていたのが、「聴くときは充分に注意を払ってただ聴く」というように変わりました。こちらが柔らかくただ受け止めるような態度になると、話し手も同じように柔らかくなるような感じがします。マインドフルな態度というのは、その場にいる方に広がっていくといえば良いのでしょうか。
宮本
カウンセラーのあり方が、その場の雰囲気全体に影響を与えると。
羽根さん
そうですね、例えば、私自身もカウンセリングをしながら、ソワソワしているな、と感じることがあります。そのときは、そのことに充分に気づいてあげると、そのソワソワがだんだんと自分の中で落ち着いていきます。そのことに気がついていないと、ふわふわした状態で、相手の方の発言や様子に私自身が巻き込まれてしまい、それがまたクライアントに伝わり、その場全体が落ち着かない感じになりかねません。
その時に、自分自身に「プレゼンス(存在感、今ここにあること)」があり、そこにただ落ち着いている、存在している、ただ聴いている、という状態であると、その場全体が落ち着いていきます。クライアントにとっては、対話の内容も大事ですが、その場の中にいられる事自体もサポートになるのだと思います。
宮本
ちなみに、ご自身がプレゼンスを保ち「今ここ」にとどまるために、どのようなことをされるのですか。
羽根さん
例えば、始まる前に3分くらい呼吸に注意を向けてセッションを迎えるように準備をしたり、カウンセリング中であれば足の裏に感覚を向けてみたりします。そうすると、下の方に重心が下がっていくような、安定して、オープンな感じになります。
あと、トレーニングの中でもあった「間を取る」ということがとても自分自身のサポートになっています。クライアントはお困りのことがあってこられるので、感情が高ぶっていて早口でお話になるような場合もあります。そんなときは、聴き終わったあと、いったん静かに間をとると、場の雰囲気も落ち着きますし、しっかりお話を聴きましたよということをお伝えすることにもなりますし、自分のなかで自然と必要な言葉が浮かんできます。
その間をとる、ということが、自然に自分のなかにでてくるようになりました。これは、トレーニングの中で、それを実際に体験したからだと思います。
感情のエネルギーが強い状態で話された内容というのは、視野が狭い主観的なところになりがちなのですが、間を取ることにより、クライアントも、私自身も、視野が広がり、上手に距離を取りながら、次に移っていけるようになるように感じます。
宮本
先ほど質問した話と重複しますが、あらためて、カウンセラーの仕事とはどういうものだと思われますか。
羽根さん
私の理想は、カウンセラーというのは、クライアントが困ったときにいつでも相談にこれる存在である、ということです。そういう人がいる、という存在感が、そのクライアントの中にあることだと思います。この人なら相談しても大丈夫、という安心感というか存在感です。Amir先生も、マインドフルネス講師のあり方を「クライアントにとっての鏡である」という例え方をされましたが、確かにそうだなと思います。
宮本
カウンセラーとして、クライアントがどう感じたり、どうなったりしたら、カウンセラーとして役割を果たしていると思いますか。
羽根さん
私は、北欧に興味があり、フィンランドの研修などもうけているのですが、そこでよくでてくるように、クライアントがウェルビーイングな状態になることかなと思います。
宮本
カウンセリングはウェルビーイングのためにどのようなサポートになりますか。
羽根さん
子育て中の保護者や幼稚園の先生などが、ウェルビーイングに近づいていく一つのポイントは、周りの人の目よりも自分自身の価値観に気づいてそれに従っていくということだと思います。周りの目が気になって、という話はよく聞きます。外に向けている目を、内側に向けて行くという、シフトがあるとよいのだろうと思います。
宮本
カウンセリングは、そういう視点のシフトにつながる可能性があるということですね。クライアント自身はどんなことを求めてカウンセリングにやってこられるのでしょうか。
羽根さん
やはり具体的な困り事があってお見えになるので、次にどうしたらよいか、ということを知りたいのだと思います。そのような場合は、私は、ある事象についてそのことのポジティブな面を一緒に見ていただくお手伝いをしたりします。
そうすると、先程のような、視点のシフトまで自然と行く方もいらっしゃいます。
宮本
そこにカウンセラーとしてのプレゼンスが必要なのですね。
羽根さん
現代に住む私たちは、忙しい生活の中で、Doingモード(注:目標を達成するために何かを追いかける心の状態)で過ごすことが多く、これは忙しい学校の教育現場でも同じです。それを時々Beingモード(注:ただそこにあり、感じる心の状態)でいられるようにすることがサポートになると思います。カウンセラーという役割は、そういった「ただある」というモードを体現する存在になれると思います。そうすると、その教育現場にいる忙しい皆さんにも、少しずつBeingな柔らかさや、やさしさが広がっていくのではないかと思います。
以前、経験豊富な臨床心理士の先生が、私たち後輩に向けてかけてくださった言葉があります。それは、「スクールカウンセラーは、その日に出勤したら50%は達成している」というようなことでした。その話を聞いていた人がみんな子育て中の臨床心理士で、出勤すること自体が大変な状況だったのでそのようなことを言ってくれたんだと思うのですが、その言葉は私の中では今でも印象深く残っています。
何より、そこにいるという存在感が大切なのだな、ということです。
宮本
私も、最近娘のことで学校のスクールカウンセラーの先生にお世話になりました。おっしゃるように、相談できる相手がいる、その存在感というのはとても大きいなと感じます。それは、話していただく内容もそうなのですが、嘘がない、信頼できる、子どものことを第一に考えてくれて、向こうの考えるようにコントロールしようとしているのではない、と感じられることがそれと同じくらい大事だと感じます。
羽根さん
私たちカウンセラーがそういう存在であるためには、マインドフルネスは欠かせないなと思います。自分が、クライアントの感情に揺れ動いていたら、クライアントは安心感を感じることはできないだろうと思います。
そういえば、このトレーニングの課題図書として読んだSitting Togetherという本もとても助けになりました。瞑想が難しいという方にも、短い瞑想のやりかたなども書かれてありました。これからも、マインドフルネスの実践を通じ、プレゼンスを養っていきたいと思います。
宮本
本日はありがとうございました。
より深く学びたい方へ
6月開講、”プレゼンスの力”、詳細は以下バナーより。