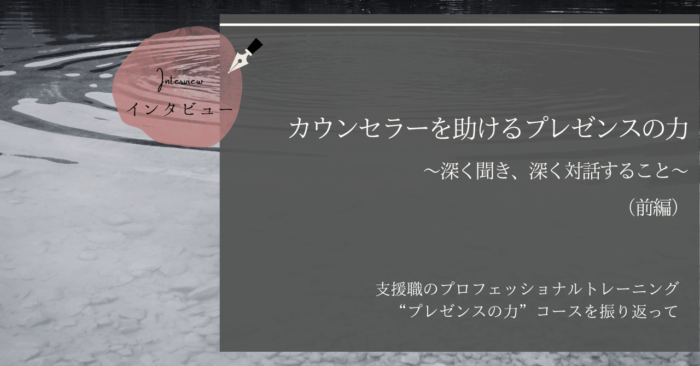International Mindfulness Center JAPANでは、マインドフルネスストレス低減法(MBSR)、マインドフルネスマインドフルネス認知療法(MBCT)を始めとした各種プログラムをご提供しています。その中で、心理支援職に向けたプログラムとして2023年に「プレゼンスの力」を開講しました。
前後編2回でお届けします。まずは前編です。
このプログラムに参加いただいた、臨床心理士の羽根さんにインタビューをさせていただきました。
(インタビューアー:IMCJ宮本)
宮本
本日はご多用のところ、ありがとうございます。ちょうど今は、マインドフルネスマインドフルネス低減法(MBSR)のトレーニングも、年明けから実際にMBSR8週間コースを教える段階に来て、お忙しい時期ですね。
さて、今回は2023年にご受講いただいたトレーニング「プレゼンスの力」について、ご参加いただいた体験をお伺いしたいと思い、お時間をいただきました。
羽根さん
よろしくお願いします。
宮本
さて、今は心理の専門職としてスクールカウンセラーやキンダーカウンセラーとして活動されていると伺っています。そもそも、どういった経緯で、心理の専門職という仕事を目指されたのか、というところからお伺いしてもよろしいでしょうか。
羽根さん
はい、私はもともと子どもが好きで、いまも子どもに関わる機関で、スクールカウンセラー、キンダーカウンセラーとして仕事をしています。私が高校生ぐらいのときに、子どもが虐待されているというようなニュースを目にする機会が多く、そのときに、子どもが大切にされてないっていうことがすごいショックでした。そうして子どもに関わる仕事をしたいと思っていたときに、友達が臨床心理士という職業について教えてくれました。
実は、高校に入学した頃は、小児科医になりたいと思っていました。ただ、色々考えているうちに、臨床心理士のほうが自分にとってやりたいことにあっているかなと感じて、そちらの方に進みました。
宮本
それで、大学から大学院までそのまま進まれて、心理士になられたのでしょうか。
羽根さん
はい、そして、卒業後は、まず、今で言う児童心理治療施設で、子どもの面接とか、グループワークなどをやっていました。そこは、入所されているお子さんや、通いのお子さんがいて、そういった子どもを心理的にサポートするという仕事でした。例えば、不登校の子どもとか、児童養護施設で他の子どもと生活するのが難しいような子どもたちがきていました。その仕事を2年していて、2年目からはスクールカウンセラーも始めました。
宮本
そのお仕事はその後どうなったのですか。
羽根さん
その頃、私自身の結婚、妊娠というタイミングが重なり、いったん、仕事をやめました。そして、数年後、復帰したタイミングで、小学校のカウンセラーに復帰し、その後、幼稚園のカウンセラーになりました。いくつかの小学校や幼稚園を掛け持ちして、子どもや保護者、先生の心理的なサポートのために定期的に訪問しています。
宮本
高校生の頃に思っていたことを、いまもそのまま一貫してお仕事して行われているのですね。大人向けと子供向けでは、サポートの仕方も異なりそうですね。
羽根さん
キンダーカウンセラーとして多いのは、幼稚園の先生から相談を受けて、子どもの様子を見ることです。そのときは、私自身も子どもの中に入って一緒に遊んだりしながらその様子を観察します。スクールカウンセラーとしては子どもにカウンセリングをすることもあります。また、いずれの場合も、先生や保護者のカウンセリングを行うこともあります。
宮本
それで、前回ご受講いただいた「プレゼンスの力」、では、どのようなことが印象に残っていますか。どのようにご自身のサポートになったと感じられますか。
羽根さん
まずぱっと思い浮かんだのは、仕事の時の疲れ方です。それまで、カウンセリングをしたあとは、頭が痛くなるようなことが度々ありました。それが、「プレゼンスの力」のトレーニングを受けたあとは、マインドフルに聴く、ということを実践すると、カンセリングしても頭が痛くならなくなって、楽な感じがしました。
宮本
それは、ご自身のなかで、どんなことが起きていたのでしょうか。
羽根さん
以前は、相手の話を聞きながら、頭で聞いていたのだろうと思います。次にどのようなことを返せばいいかな、というようなことが頭の中に沢山浮かんでいました。しかし、このトレーニングのあとは、もっと体全体で聴いている、という感じがします。トレーニングの中でAmir先生といっしょにマインドフルに聴くことや対話を実践する中で、体で聴くということを、体感していった感じです。
いまは、クライアントが話しているときは、聴くことに充分に注意が向いている状態だと思います。
宮本
普通の会話だと、話を聴いて、次に話す、ということをします。ですから、話を聞きながら次に話すことが浮かんでくるというのは、日常の会話ではある意味自然なことだとも思うのですが、ただ聴くことに注意を向けるという聴き方をすると、会話としてどのようなことがおこるのでしょうか。
羽根さん
聴き終わったあとに、自分の中に自然と浮かんできたことを選びながらお話するようになりました。先日行われたMBSR講師養成のトレーニングの中で行った対話トレーニングのときにも話題になっていましたが、困り事のあるクライアントのお話を聞いているときというのは、聴きながら「こうしたらこの人が幸せになるんじゃないか」とか「こうしたほうがいいんじゃないか」というような、ある方向に導きたくなるような思考が浮かんでくることがあります。
そういったアドバイスをして特定の方向にクライアントを連れていくということではなく、より、自分の内側からでてくることをお返しするような感じです。
宮本
そうなると、カウンセラーという役割は、話を聞いて助言を与える人、という役割よりも、また別の役割をもっていることになりそうですね。それはどんなことなのでしょうか。
羽根さん
そうですね、確かに、これまで、私にとってのカウンセラー像は、聞かれたら何かを返すのが仕事、という意識が強かったのだと思います。それが力みにつながっていたように感じますが、今回のトレーニングを経て、それが軽くなり、自分自身が柔らかくなったように感じます。
特に子ども向けのカウンセラーの仕事というのは、必ずしも、アドバイスを与えることが重要というわけではなく、彼ら彼女らの日常に入っていって、一緒に話をするということ自体が支援になるという側面があると思います。
宮本
カウンセラーの役割はいくつかあるのだと思いますが、一つは話を聴くだけでも支援になるということですね。
羽根さん
最近、ある中学校で、学年全員と一対一で面談する機会がありました。最初は、「知らない大人と話したくない」と言っていた生徒もいたようなのですが、実際に話しをしてみると、「継続的に話をしたい」という子どもが何人かいました。
実際に話しをしてみて、この人とまた話せる、何かあればこの人に相談すれば良い、というように思ってもらえる、そういう存在であることが、カウンセラーとしての役割の一つだと思います。カウンセラーがそういう存在になれれば、子どもに、安心感をもって毎日を生活してもらうことができるようになると感じます。
こういうこともありました。以前、ある小学生が、クラスの人間関係に悩んでいました。その子は、私が授業を見に来てくれるだけで安心する、と言ってくれていました。その場で何か話すわけでもないのですが、それも、私の存在が何かしらその子に伝わった、ということなのだと思います。
そういうことが大事なのではないかと思います。
宮本
なるほど、その存在自体がサポートになるということですね。子どもからすれば、コントロールしようとしてくる大人ではなく、ただ自分のいうことをそのまま聴いてくれる安心感ということなのでしょうね。
羽根さん
学校だと、大人と子ども、先生と子ども、という関係性が、場合によっては力関係にもなります。そこで少し違う立場のカウンセラーがいることの意味は大きいように思います。
より深く学びたい方へ
6月開講、”プレゼンスの力”、詳細は以下バナーより。